この記事では「TMS」について詳しくご紹介いたします。
「TMSとWMSの違いが全く分からない」
「具体的に実務に使うにはどうすればいいの?」
「TMS導入についての選ぶポイントはあるの?」
という方のために、基本的な考え方やポイントを具体例を交えて徹底解説します。
「配送に時間がかかってしまっているので、もっと効率よくドライバーに運送させたい」
という方から「TMS??なにそれ有効なの?」という方まで誰でもTMSが理解できるように記載しております。
TMSとは

TMS(Transport Management System)とは、輸配送管理システムとも言い、クラウドの形などで物流における配送の工程を一括管理するシステムのことを指します。
コロナ禍をきっかけに多くの人の在宅時間やオンラインショッピングの利用が増加しました。それに伴って、配送業の業務量も大幅に増えました。
従来は配車、積み込み、運送センターへの運輸、配送センターから小売店やエンドユーザーへの配送など、それぞれの工程ごとに管理をしていた物流業ですが、今日のように扱う製品の増加・複雑化が進む中で、以前と同じ方法で管理を行うことは難しくなってきています。
そこで、各工程をバラバラに管理するのではなく、俯瞰的に全ての工程を一括で管理できるTMSが新たなソリューションとして注目されています。
TMSはどんな悩みを解決してくれるのか?

ではTMSは具体的にどのような悩みに対して有効なのでしょうか。
従来、配送を行う際の効率的なルート選定や荷積みなどは、現場のベテランの豊富な経験や勘を頼りに行われてきました。しかしながら、属人的なリソースに頼って物流環境を整えるには、社会から求められる物流の需要はあまりにも多くなってしまっています。また、いくらベテランと言えども、状況の判断にばらつきが生じたり、ヒューマンエラーを起こす可能性を完全に取り除くことはできません。
そのような状況において、TMSを導入することは非常に有効的な対策となります。適切な配送量の計画立案、その都度の交通状況に応じたルート選定、3Dでの積載シミュレーションなど、最も効率的な物流計画を安定的に確立することが可能となるからです。
WMSとの違い
一方、TMSと似た用語としてWMSがあげられます。こちらはWarehouse Management Systemの略で倉庫管理システムのことを指します。倉庫内部での物の動きを一括管理するシステムがWMS、倉庫を離れた後の配送の段階を一括で管理するシステムのことをTMSと言います。これら2つの物流システムをスムーズに連携・運用することで無駄を省いた物流環境を実現することが可能になります。

TMSの機能の詳細

TMSを導入することは様々な面で変化をもたらしますが、特にその中でも主な機能を3つご紹介致します。
システム管理と車両の選定

荷主からの発送・発注情報を一元的に管理し、それに基づき適切な車両の手配・割り振りを行います。それぞれ届け先の異なる大量の荷物を効率的に捌くために、適切な車両を選定し、業務指示を出すだけでも、属人的な手段で行えば膨大な業務量になってしまいます。結果として最適とは言えない車両選定を行ってしまったり、長時間勤務などドライバーへの負担が過重になってしまうケースもありますが、TMSを使用すると短時間でベストに近い解答を弾き出すことが可能になります。
配送ルートの作成
最も効率的な配送経路を選定します。最短距離を弾き出すだけではなく、渋滞情報や、顧客の配送希望時間なども計算に入れルートの選定を行います。また、ルート選定も一度作成してそこで終わりではありません。倉庫から出発した後も、交通状況などを反映しながら、より効率的なルートになるよう随時アップデートを行い、その時々での最適なルートをドライバーに提案することが可能です。

配送運賃の計算

ドライバーに支払う運賃の計算や請求書などの資料作成も簡単な業務ではありません。走行時間・距離からの算出に加え、地域間での運賃の違いや残業手当てなど、多くの考慮すべき点があるため、事務作業にも労働力・時間を要します。しかしながら、TMSだと諸条件の入力を行えばあとは自動で計算を行うため、人件費の削減にも繋がります。
TMS導入のメリット・デメリット

続いてはTMSを導入することによって生じるメリットとデメリットを具体的に確認していきましょう。
TMS導入のメリット
TMS導入のメリットは以下の通りです。
配送計画の効率化・省人化

これまでベテランの現場作業員やドライバーの経験に拠るところの大きかった配送計画の立案。現場の生の声を反映できるというメリットはある反面、一部の担当者へ多くの負担がかかってしまったり、統一化されたマニュアル的な運用が難しいという懸念点がありました。TMSを導入することで事務の担当者でも立案・管理ができるようになるため、現場担当者が現場の業務に専念することが可能になります。
また作業工程の削減により、人件費・物流コストの削減も期待することができます。
ドライバー業務の効率化
荷積みを終え、倉庫から出荷された後はドライバーの業務状況を把握できなかったのが従来の配送業ですが、TMSを導入することで運転中のドライバーの状況をリアルタイムで追跡し、より効率的な配送に繋げることができるようになります。
荷主などの管理側からは、その都度の交通状況などを反映したルート修正の指示等をドライバーの持つ端末に送ることができます。また、ドライバー側の端末からも、配送の進捗具合の連絡や、安全な配送を行うための居眠りチェックセンサーなどの情報を管理側に発信できるため、相互に業務状況を把握し合うことが可能になります。

トラックバースの混雑の緩和

配送センターでトラックが荷物の積み下ろしを行う場所のことをトラックバースと言います。トラックバースは数が限られているため、ある程度の順番待ちになってしまうことは仕方がないこととされていました。しかし、この待ち時間のために、ドライバーの労働時間は長くなってしまう傾向にありました。TMSを使用することにより、トラックバースの混雑状況を事前に確認し、予約などができるようになるため、労働力のロスになっていた時間の削減に繋がります。
またトラックの実働時間が減ることにより、排気ガスの排出量も削減することができるようになります。
TMS導入のデメリット
下記がTMS導入のデメリットです。
コスト

TMS導入にあたっての一番の懸念点はコストでしょう。導入の程度にもよりますが、システムの導入には決して安いとは言えない費用が必要となります。
またシステムそのものにかかる費用の他に、現行の物流体制を変更する際に生じるコストも考えなければなりません。物の流れの以外にも、人員配置替えに伴う費用など、トータルでかかる費用を精査した上で、導入するかどうかを検討しましょう。
ノウハウ流出の可能性
上記でベテランの経験値に頼り切るのではなく、システムとして一元管理するメリットをお伝えしましたが、100%システム頼りになることも多分にリスクをはらんでいます。どれだけ技術が進歩しても、機械やシステムで差配することのできない部分は必ず残ります。それに対処できる人材の流出を防ぐと共に、元々保有していたノウハウを引き継いでいける環境を整えることも、AI時代における重要なリスクヘッジと言えるでしょう。

TMSを導入する際に気をつけるべきポイント

車両選定、運行ルートの作成、積み込みシミュレーション、ドライバーとの連携、運賃の計算など、ここまでTMSが持つ様々な機能を見てきました。
しかしながら、これらの機能は全て一つのシステムで運用できるわけではなく、各々の分野に特化したシステムがあり、いずれを導入するかによって利用できる機能が異なってきます。
そのため、自社内の状況を分析し、導入の優先順を慎重に検討する必要があります。
「ルート構築を担当しているベテラン作業員の定年が迫ってきている」
「既にベストなルートを構築できる担当者がいない」
などの場合は、ルート構築に特化したTMSの導入を優先した方が、全体で見たときのメリットは大きいでしょう。
一方で、荷運びの工程には現状課題は抱えていないものの、運賃計算を担当する事務スタッフが不足しているという会社もあることでしょう。
その場合、導入の優先順位は当然前者とは異なってきます。
自社が抱えている課題を見つめ直すにあたって、第三者の視点を借りることも一つの手です。
物流コンサルティングや、TMSを提供する企業へ相談してみることで、今まで気が付かなかった解決策を見つけることができるかもしれません。
TMS導入事例
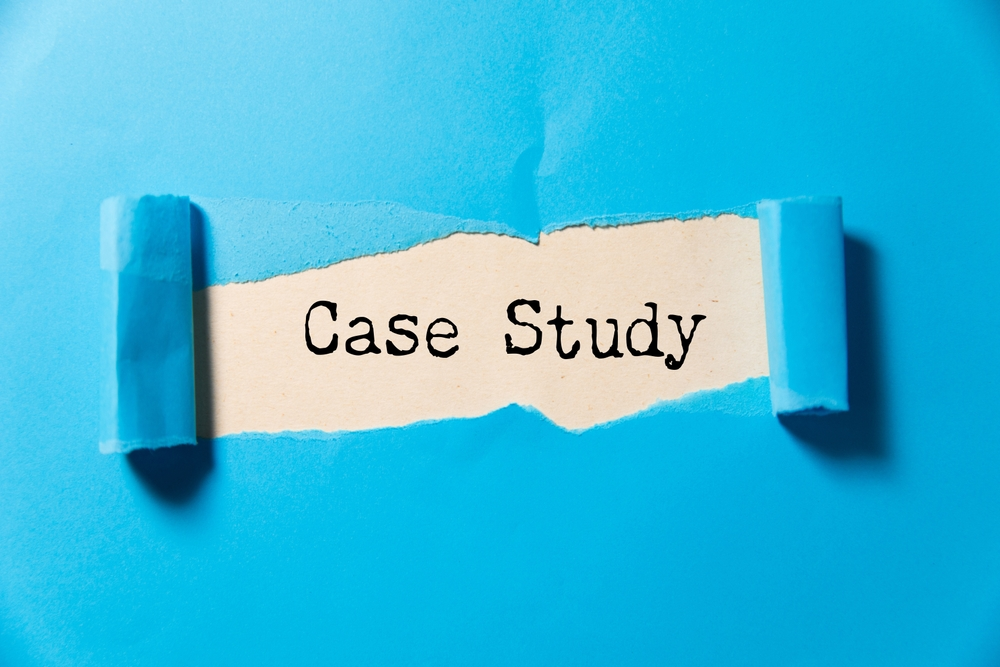
最後に、実際のTMS導入実績をいくつかご紹介いたします。
大手コンビニチェーン

従来、配送車両が渋滞に巻き込まれた際、ドライバーからの連絡で状況が発覚するのが通常でした。連絡後に輸送ルートの修正や、届け先への遅配連絡を行う形となり、場合によってはクライアントの販売機会の喪失になってしまったり、クレームなどの問題に繋がるケースもありました。
しかしTMSを導入することにより、センター側で解析するビッグデータから渋滞情報を事前に察知し、支援車両の手配、前もっての配達時刻変更の連絡を行うことでトラブルを起こすことなく配送を完了させたケースがあります。
運輸業界の倉庫業務
続いては、TMSが配車・トラック回転率の向上に一役買った事例をご紹介いたします。
受注日の翌日午前の配達に対応するため、弊社が業務提携を行っている運輸会社の倉庫では午前9時台での積み込みが集中していました。しかしながら全てのトラックが同時にトラックバースに入ることはできないため、荷積みでの渋滞や、待ち時間での長時間労働になってしまうケースもありました。ところがTMSを導入し改善を重ねたところ、配車管理は180分から20分へ短縮、トラックの回転率は1.2から1.7に改善しました。効率のアップから、配送時間の前倒しや、取扱量の増加にも成功しました。
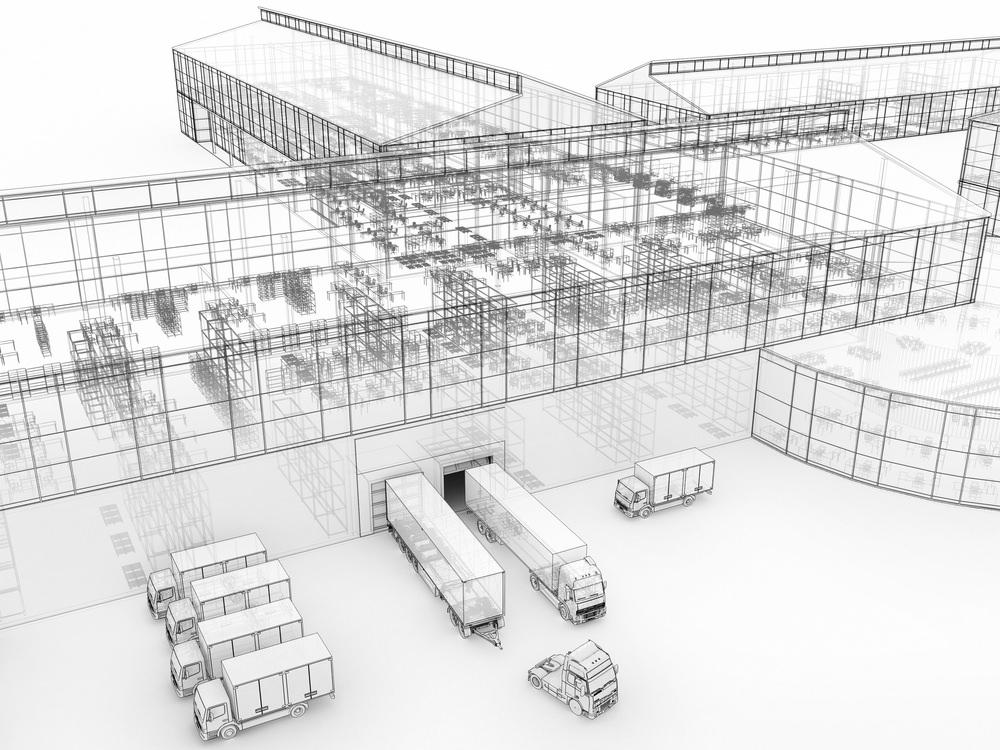
貨物配送業者

TMSは配送過程での効率アップにも効果的です。
弊社が提供するTMS、Quentを利用する貨物配送業者では、ドライバーにシステムをインストールしたスマートフォンを貸与しています。それを利用し、ドライバーの現在地や滞在時間の把握、荷物の積み下ろしの進捗管理などを行っています。配送途中の情報も逐次センターと共有できるため、生産性の向上を図ることが可能です。
また、Quentは学習機能も備えているため、データを蓄積・活用することで、回数を重ねるごとに指示もより的確になってきていきます。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
TMSと一口に言っても様々な機能が存在し、それぞれに得手不得手があります。自社が必要とする機能を的確に見極め、導入を行うことでメリットの最大化を図ることができますが、それは容易なことではありません。
外部の視点を導入することも、新しい気づきに繋がります。
弊社では物流のプロフェッショナルによるコンサルタントティングも行っております。TMSの導入を検討されている事業者様は、是非とも一度ご相談ください。
ロジスティクス大賞の受賞で裏付けられる
技術とノウハウ
シーオスは、公益社団法人 日本ロジスティクスシステム協会が主催する「 ロジスティクス大賞」を2度受賞しています。
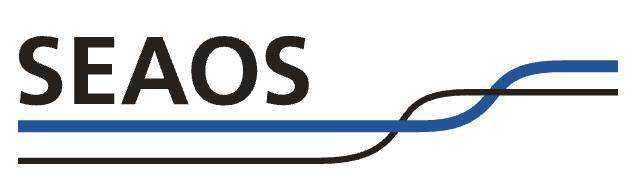





コメント